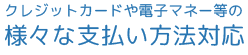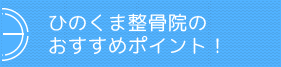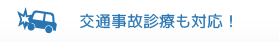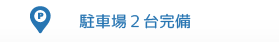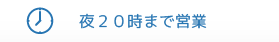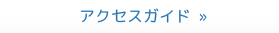足の裏が痛む「足底筋膜炎」という診断を受けたことがある方も多いかもしれません。しかし、実際に臨床の現場では、本当に炎症が起きているケースは少ないのです。本記事では、足底筋膜炎の発症背景と、足の痛みの本当の原因について詳しく解説していきます。
そもそも足底筋膜炎とは?
一般的に、「足底筋膜炎」とは、足の裏にある「足底筋膜」と呼ばれる腱膜が炎症を起こし、痛みを発するものとされています。特に、ランニングや長時間の立ち仕事、加齢による足底の負担増加が主な原因と考えられています。
しかし、実際に臨床で診察すると、多くの患者さんに炎症の特徴である「熱感」や「発赤」が見られません。このことから、足底筋膜炎という名称が、必ずしも正確な診断名ではない可能性があるのです。
炎症ではなく「筋肉・靭帯の緊張」が原因?
足底の痛みの多くは、「炎症」ではなく、「筋肉や靭帯の緊張」による牽引痛やコリの痛みであることがほとんどです。特に、以下のようなパターンで痛みが発生することが多いです。
- 走っている途中から徐々に痛くなる
- 休憩後、歩き始めに痛みが出るが、動いていると軽減する
- 常に痛みがあるが、特定の動作で強くなる
このような痛み方は、純粋な炎症反応とは異なり、足底の筋膜や靭帯が過度に緊張し、血流不足や神経の過敏化を引き起こしている可能性があります。
足底筋膜炎と診断されるメカニズム
医学的には、足底筋膜炎は「足の縦アーチが崩れることで、足底の筋膜に負担がかかる」と説明されることが多いです。しかし、この理論にはいくつか疑問が残ります。
- 足底のアーチが完全に崩れるには、スプリング靭帯が伸び切らなければならない → 実際には、そこまで極端なケースは少ない。
- 浮き指(つま先が上がる状態)は、足底の炎症ではなく、足の伸筋腱の緊張によるもの → 足底の炎症がなくても、足の使い方次第で発生する。
- 診察すると、ほとんどの患者さんに炎症の特徴(発赤・熱感)が見られない → つまり、炎症ではなく「筋肉の過緊張」が痛みの原因である可能性が高い。
かかと重心が引き起こす足の不調
足底の痛みを訴える方の多くに共通するのが、「かかとに荷重がかかりすぎている」という特徴です。かかと重心になると、体のバランスを取るために以下のような変化が起こります。
- 指を浮かせる(浮き指) → つま先が地面に接地しないため、足のアーチが崩れる。
- 指を丸めて力を入れる(槌指) → 逆に、バランスを取るために指が過剰に緊張する。
- 足首の可動域が狭くなる → かかと荷重が強まることで、足首の柔軟性が低下し、正常な背屈(足首を上に曲げる動作)ができなくなる。
この状態が続くと、足底の筋肉や靭帯に過度な負担がかかり、痛みが発生します。
改善策:足首の可動制限を解除する
足底の痛みを軽減するためには、まず「足首の可動域を正常に戻すこと」が重要です。そのためには、以下のような施術やケアが有効です。
- 足首を大きく回すストレッチ → 足首周りの筋肉をほぐし、柔軟性を高める。
- リスフラン関節(足の甲の関節)の動きを改善する → 硬くなった関節をほぐし、足全体のバランスを整える。
- 荷重バランスの改善 → かかと重心を改善し、足の指をしっかり使えるようにする。
ひのくま整骨院での施術
ひのくま整骨院では、「足底筋膜炎」と診断された方でも、実際には筋肉や靭帯の緊張が原因であることが多いため、炎症を抑える施術ではなく、筋肉の緊張を和らげ、関節の動きをスムーズにする施術を行います。
- 神経筋整復法による施術 → 足の使い方を正常に戻し、痛みの原因となる神経の過敏化を抑える。
- 荷重バランスの調整 → かかと重心を改善し、足全体でバランスよく体を支えられるようにする。
- 施術前後の姿勢のチェック → スマートフォンを活用し、施術前後の変化を視覚的に確認できる。
まとめ
足底筋膜炎と診断されても、実際には「炎症」ではなく「筋肉や靭帯の緊張」が原因であることがほとんどです。炎症を抑えるための治療ではなく、足の使い方やバランスを改善することが根本的な解決につながります。
ひのくま整骨院では、機械を使わずに手技による施術で足の痛みの原因を見極め、最適なアプローチを行います。「足底筋膜炎」と診断されたものの、なかなか痛みが改善しない方は、ぜひ一度ご相談ください!2025